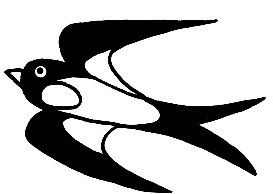神戸市教育委員会
幼保小の学びの接続
最終更新日:2025年3月3日
ページID:49698
ここから本文です。
神戸市では、園種を超えた幼児教育の充実と、一人ひとりの子供たちの学びを小学校就学以降に円滑につなぐ「幼保小接続」に取り組んでいます。
以下の観点で、幼保小接続の取り組みを「神戸つばめプロジェクト」と名付け、市立小学校および公・私立の認定こども園や幼稚園、保育所(園)の校園種を超えた取り組みを進めています。
- 教職員、保護者、地域の人々みなさんが子供をともに見守り育てる
- 世界に羽ばたき、神戸をふるさととして大切に思う心を育てる
小学校教育への接続を踏まえた「幼児教育の充実」
市立幼稚園では、標準的で質の高い幼児期の教育の実践及び発信に取り組むことで、認定こども園や幼稚園、保育所(園)と共に、神戸市全体の幼児教育の充実に取り組んでいます。【取り組み事例:1】幼児期に育みたいこうべっ子の資質・能力研究
実践園4園のうち、2園の公開保育と実践発表、講演会が実施されました。神戸市内の公・私立の幼稚園、保育所(園)、認定こども園、小学校の教員・保育士が参加し、幼児期や接続期の教育について話し合い、学びを深める貴重な機会となりました。
2024年度研究発表・公開保育の開催結果
- 11月20日(小束山幼稚園にて公開) 講演会:元 兵庫大学 教授 藤原 照美 氏
「感じて 伝えて つながって ~人との関わりを喜び、楽しむ子供に~」のテーマで「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」の視点からみとる実践についての発表がありました。幼児期の経験や育ちが小学校以降の学びにつながっていることを再認識する機会となりました。
- 11月27日(淡河好徳幼稚園にて公開) 講演会:兵庫教育大学大学院 教授 石野 秀明 氏
「豊かな環境に自ら関わり、意欲的に遊ぶ子供をめざして ~造形遊びを通して、思いを豊かに表現するための環境の構成について考える~」のテーマで「豊かな感性と表現」「自立心」の視点からみとる実践についての発表がありました。思いを豊かに表現するための環境の構成について話し合い、幼児の主体的な活動を支える教師の役割についての重要性を改めて感じる一日となりました。


【取り組み事例:2】「運動遊び研究指定園」研究協議会
2025年1月22日、研究指定園の玉津第二幼稚園で、「心も体も弾ませよう とことん遊ぼう 玉二っ子~友達との関わりの中で、健やかな心と体の育ちを支える教師の援助を探る~」のテーマでの公開保育と研究協議会、伝達講習会が実施されました。神戸市内の公・私立の幼稚園、保育所(園)、認定こども園、小学校の教員・保育士が参加し、幼児期や接続期における運動遊びについて話し合い、学びを深める貴重な機会となりました。
【取り組み事例:3】校園種を超えた研修(つばめセミナー)
「つばめセミナー」は、神戸市内の公・私立の幼稚園・保育所(園)・認定こども園・小学校(義務教育学校)の保育士・教員が校園種を越えて合同で研修し、神戸市全体の教育の充実を図っていくことを目的として2016年度から定期的に開催しています。毎回多数の保育士・教員が参加し、資質向上を目指して共に学んでいます。
2023年度から保育士等キャリアアップ研修にも対応し、幼児教育と小学校教育の接続期に関して研修を進めています。
2024年度セミナー開催結果
- 第1回つばめセミナー(8月21日 講師:神戸大学附属幼稚園長・小学校長 田中孝尚氏)
「幼児期の学びと児童期の学びをつなぐ架け橋期の教育」と題して、ハイブリッド研修(集合型、オンライン型の複合型研修)を行いました。公・私立の幼稚園・保育所(園)・認定こども園・小学校の様々な施設類型から集合型約40名、オンライン型20名、計60名の参加者が熱心に参加しました。
<受講者の感想>
- 小学校の先生と語り合いながら、互いの教育のよさを分かり合えるようにしていきたいと思いました。
- 今年度、1年生担任として幼小連携の重要性を改めて実感している。夏期休業中に地域の幼保へ伺い、遊びの中での気付きから学びにつなげていることを聞き、授業づくりなどにおいて意識していく必要があると本研修でも再認識することができました。

- 第2回つばめセミナー(9月25日 講師:神戸大学大学院人間発達環境学研究科 北野幸子教授)
「乳幼児教育の遊びを通した学びについて考える―小学校教育を見通しながらー」と題して、ハイブリッド研修(集合型、オンライン型の複合型研修)を行いました。公・私立の幼稚園・保育所(園)・認定こども園・小学校の様々な施設類型から集合型約55名、オンライン型25名、計80名の参加者が熱心に参加しました。
<受講者の感想>
- 準備教育、早期教育、前倒し教育ではないということを発信していく大切さを感じました。子供たちが自分で選べる、考え工夫できる、そういう保育をしていきたいと思います。
- 改めて幼児期の学びの大切さを感じることができました。今後も幼児期の教育・保育について学び、小学校の教育に生かしていこうと思います。

- 第3回つばめセミナー(10月16日 講師:神戸大学大学院人間発達環境学研究科 渡邊隆信教授)
「接続期にふさわしい遊びを通した教育ー道徳性の育ちを中心にー」と題して、ハイブリッド研修(集合型、オンライン型の複合型研修)を行いました。公・私立の幼稚園・保育所(園)・認定こども園・小学校の様々な施設類型から集合型約40名、オンライン型20名、計60名の参加者が熱心に参加しました。
<受講者の感想>
- 幼稚園でも幼児なりに話し合うことを積み重ねていきたいと思いました。
- 1年生の素直な考え方や表現を保ちながら学年を経ても、生活に密着した道徳の授業ができるようにしたいと思いました。また道徳性が培われるために幼児期の遊びが非常に重要だと再認識しました。

- 第4回つばめセミナー(11月6日 講師:神戸大学附属幼稚園 浅原麻美 教諭)
<受講者の感想>
- 幼児理解を深め、自分の援助を振り返るために、記録を書いて評価していくことの大切さを改めて感じました。
- 幼稚園の取り組みを知り、改めて細やかな評価を毎日、毎時間されているなと感じた。保護者に分かりやすいように、そして、次の授業や指導に生かせるよう、評価や記録を今後もしていきたい。

- 第5回つばめセミナー(12月18日 講師:神戸大学大学院人間発達環境学研究科 岡部恭幸 教授)
<受講者の感想>
- 数量認識の育ちを支えるためには、幼児期に自由な遊びの中で、数量にふれる経験をたくさんしておくことが大切だということがよく分かりました。そのような経験が生まれていくように教師が意識して環境づくりをしていくことが大切だと学びました。
- 数量認識を教え込み苦手意識をもたせるのではなく、やってみたい!しりたい!と思える遊びの中からの展開がとても大事なのだと改めて感じました。

- 第6回つばめセミナー(1月28日 講師:神戸大学大学院人間発達環境学研究科 目黒強 准教授)
<受講者の感想>
- 絵本の中で使われているオノマトペの効果や大切さを知り、これから絵本を選ぶ時や読む時に意識したいと思いました。
- 絵本とオノマトペの効果について、考えるきっかけになりました。答えは無いけれど、絵本で出てくる言葉について「こんな効果があるかもしれない」と考えるのは大事だなと思いました。

幼児期の学びを引き継ぐ「小学校教育の充実」
公・私立の認定こども園や幼稚園、保育所(園)が協調して幼児期の教育を行っている神戸市では、子供たちが多様な施設から小学校に入学します。
市立小学校では、幼児期で子供たちに育まれてきたことが円滑に小学校での教科などの学習に接続されるよう、特に入学当初における指導の工夫などに取り組んでいます。
【取り組み事例:4】スタートカリキュラムの作成・実践
幼児期の遊びを通じた総合的な学びが各教科などでの学習に円滑につなげられるよう、各市立小学校ではスタートカリキュラムを作成し、実践しています。【取り組み事例:5】幼児教育の理解等を通した小学校の学級経営・授業づくりの改善
研究指定小学校での幼小合同研修会
2023年11月10日、井吹の丘小学校に学習院大学 秋田喜代美教授をお招きし、「幼小接続 幼小合同研修会(研究授業公開・授業後検討会)」が行われました。
研修1か月前の児童理解・教材研究・指導案検討の段階から研究提携幼稚園の教員が参加し、幼小が協働して授業づくりに取り組みました。

1年・算数の教材研究の様子
研修会当日は、1年国語・算数の研究授業・授業後検討会に、近隣公私立の幼稚園・認定こども園の教員が参加しました。幼小それぞれの視点から、子供の育ちや指導方法等について、活発な意見交換が行われました。

授業後の検討会の様子
園と小学校との「地域での連携・接続」
園と小学校で互いの教育内容・指導法を理解し合った上で、効果的な接続期のカリキュラムを作成・実践するため、校種間の合同研修や児童・教職員の交流、研究を行っています。【取り組み事例:6】神戸つばめフォーラム
2025年1月27日、幼児教育施設と小学校の互いの教育や幼保小接続の理解を一層促進するため、神戸つばめフォーラムを開催しました。
兵庫県教育委員会事務局からは、幼児期と児童期の円滑な接続推進に向けた、県下の幼稚園・小学校間の取り組みの紹介や幼児教育施設と小学校間における相互理解の促進について報告がありました。
また、淡河好徳幼稚園からは、「幼児期に育みたい’こうべっ子’の資質・能力研究事業」の実践発表がありました。
後半は、神戸市内の連携校園での取組(子供の交流)や幼稚園での日常のくらしが動画で紹介されました。
神戸市内の公・私立の幼稚園、保育所(園)、認定こども園、小学校の教員、保育士約240名が一同に会し、熱心に参加しました。
参加者からは、「幼稚園の生活が動画で見られてよかった」「今後も具体的な取組を聞いて参考にしたい」等の感想を多くいただきました。

【取り組み事例:7】幼保小学びの接続事業
2024年6月7日、幼児教育施設(幼稚園・保育所・認定こども園等)と小学校・義務教育学校との「子供の交流」「保育者・教員の連携」「カリキュラムの接続」を進めるための研修会を開催しました。
会の冒頭では、神戸市教育委員会から小学校における幼児教育の理解をいかした学級経営のポイントについて説明をしました。
中盤では、幼保小の協働による授業づくりについての実践発表を井吹の丘小学校山口教諭にしていただきました。
後半では、小学校の職員と小学校区等近隣にある幼児教育施設の職員との、今後の連携のための交流を行いました。
各校園の職員が所属をこえてつながることで、より一層の子供の理解が進み、有意義な実践に取り組んでいけることと思います。

![]()

「すくすく ひょうごっ子~幼児教育資料・親子ノート~」(兵庫県・兵庫県教育委員会発行)
子どもと楽しく過ごすヒントを見つけてもっと子育てを楽しみたいとき、子どもの気になる行動に関して困ったとき、小学校入学に向けて不安なときにも役立つよう、乳幼児期の育ちと関わりや小学校教育とのつながりなどが記載され、成長の様子も書き込んでいただける内容となっています。
兵庫県教育委員会ホームページからダウンロードできます。
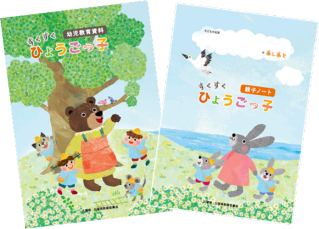
幼児教育資料・親子ノート「すくすく ひょうごっ子」(外部リンク)
- 学校生活に関する相談
- 全国学力・学習状況調査
- 神戸市情報セキュリティポリシー
- 神戸市公立学校施設整備計画
- 神戸市学校園施設長寿命化計画策定
- 開発事業区域の選定に伴う教育委員会との協議(受入困難地区、要注意地区)
- 神戸の国際教育
- 神戸の防災教育
- 人権教育
- 神戸市防犯チェックシート
- あいさつソング「ほら、つながった」
- 児童生徒等の疾病例
- 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
- 神戸市における児童生徒の生徒指導上の諸課題に関する状況について
- 神戸市教育委員会ハラスメント対策基本方針
- 全国体力・運動能力、運動習慣等調査
- 学校運営協議会、学校評議員、学校評価
- 平成29年12月22日に発生した神戸市立高等学校における学校事故に係る調査委員会
- 神戸市立小学校における職員間ハラスメント事案に係る調査委員会
- 障害者活躍推進計画
- 女性教職員の活躍の推進
- 神戸市立高等学校部活動方針
- 神戸市立中・義務教育学校部活動ガイドライン
- GIGAスクール構想(学習用パソコン)
- 平成18年2月に認知した神戸市立小学校の金銭授受等事案におけるいじめの有無及びその対応を調査する委員会
- 令和2年度神戸市立中学校生徒自死事案に関するいじめ等調査委員会
- 神戸市立中・義務教育・高等・盲学校での部活動のあり方
- 幼保小の学びの接続
- 児童生徒の心のケアのための動画
- 学校における働き方改革の取り組み
- 学校づくりの指針
- 教育長会見
- プール開放事業(2025年度は終了)
- プール開放事業_よくある質問と回答(2025年度は終了)
- 気象警報発表時の市立学校園での対応
- 体力向上の取り組み
- 学力向上の取り組み
- GIGAスクール構想による教育活動
- 教育行事に関する後援申請
- 校内いじめ問題対策委員会への外部有識者の参画
- 「今後の幼児教育・保育における市立幼稚園について(方針)」案に関する意見募集(終了)
- 市立中学校標準服のあり方の検討会 開催状況
- 神戸市立中学校標準服のあり方に関する検討会流通部会
- 神戸モデル標準服(市立中学校の制服)
- 神戸市立中学校標準服のあり方に関する検討会
- 今後の幼児教育・保育における市立幼稚園
- 就学の手続き
- のびのびパスポート
- 教科書
- 校則・標準服
- 学校保健(感染症等)
- 児童生徒への支援・指導
- 防犯・通学路の安全
- 神戸市の教育
- 計画
- 働き方改革等
- いじめ・学校事故に関する調査委員会
- 家庭・地域・学校の連携
- 広報
- GIGAスクール構想(学習用パソコン)
- 神戸市立幼稚園園則及び神戸市立高等学校学則の一部改正
- KOBE×GIGAフェスの開催報告
- 神戸市立幼稚園園則の一部改正
- 「子供が主役の学び」の実現に向けて
- 「神戸モデル標準服」販売店
- 神戸モデル標準服 届出販売店
- 「神戸モデル標準服」届出販売店を募集します【随時募集】
- 「神戸モデル標準服」製造認定メーカーの募集
- スタンフォード大学(アメリカ)との連携事業
- 神戸市立高校の入試
- 貸与規程(学習用タブレット・学習用端末・学習用パソコン)
- 令和5年度神戸市立中学校生徒自死事案に関するいじめ等調査委員会